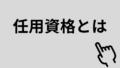重度心身障害のある方への居宅支援サービス
〜私たちが日々現場で感じていること〜
重度心身障害とは、
重い知的障害と
重い身体障害が重なっている状態をいいます。
例えば、
寝たきりで日常生活すべてに介助が必要な方や、
医療的ケア(胃ろう、吸引など)が
欠かせない方も多く含まれます。
厚生労働省の定義としては
「重度の肢体不自由と重度の知的障害を重複しているもの」
とされており、支援においては
介護・医療・福祉の連携が欠かせません。
制度面でのサポート
こうした方々には、
障害者総合支援法に基づく
居宅介護や重度訪問介護 が利用できます。
- 居宅介護(ホームヘルプ)
入浴・排泄・食事の介助など、日常生活に必要な支援を行います。 - 重度訪問介護
重度の肢体不自由で常時介護が必要な方に、長時間にわたり見守りや介助を行う制度です。
在宅での生活を可能にするために欠かせない支援です。
また、医療的ケア児支援法(2021年施行) により、
人工呼吸器や経管栄養などが
必要な子どもへの支援体制も整備されつつあります。
現場で感じること
重度心身障害のある方の介助は、
まさに 「その人に合わせたオーダーメイド」 です。
オムツの当て方ひとつでも、
拘縮や筋緊張の度合いや
側弯症の有無によって大きく違ってきます。
立位がとれない方、
上肢が硬直している方など、
体の特徴に合わせて一番楽に、
そして dignified(尊厳を守る)
形で関わる工夫が必要です。
例えば、
ある方はお風呂が大好きで、
抱えて浴槽に入ると表情が一気にやわらぎます。
緊張の強い体がふっと緩む瞬間は、
介助をしているこちらも嬉しくなります。
「生きている心地がする」
とご家族が話してくださったこともあり、
ケアの大切さを改めて実感しました。
- 重度心身障害のある方は、福祉と医療の両面から支援を受けられる制度があります。
- ケアの方法は「マニュアルどおり」ではなく、一人ひとりに合わせたやり方が必要です。
- 家族・支援者・医療職が連携することで、在宅生活の安心感が大きく変わります。
一人ひとり違う暮らしと支援
「重度心身障害」という言葉はひとつでも、
実際の暮らしぶりや必要な支援は本当にさまざまです。
オムツの当て方ひとつにしても、
さまざまです。
誰一人として同じ介助の仕方はありません。
その人に合わせた方法を探していくことが、
支援の基本です。
家族と支援者と、みんなで支える
重度心身障害のある方の生活は、
ご家族の支えなしには成り立ちません。
ただ、その介護は24時間続きますから、
ご家族の負担はとても大きなものです。
そこで訪問の支援が入ると、
ほんの少しでも「任せられる時間」が生まれます。
ご本人が安心できるだけでなく、
ご家族もふっと肩の力を抜ける。
それが居宅支援の持つ大きな役割だと思います。
最後に
「重度心身障害者(児)」
という言葉は制度上の呼び名ですが、
現場に立つと実感するのは――
そこにいるのは「障害」ではなく、
一人の生活者であり、
一人の人だということです。
支援の形は千差万別。
その人らしい安心と心地よさを探しながら、
ご家族と一緒に支えていく。
それが、私たちにできる大切な関わりなのだと思います。
徳丸でした