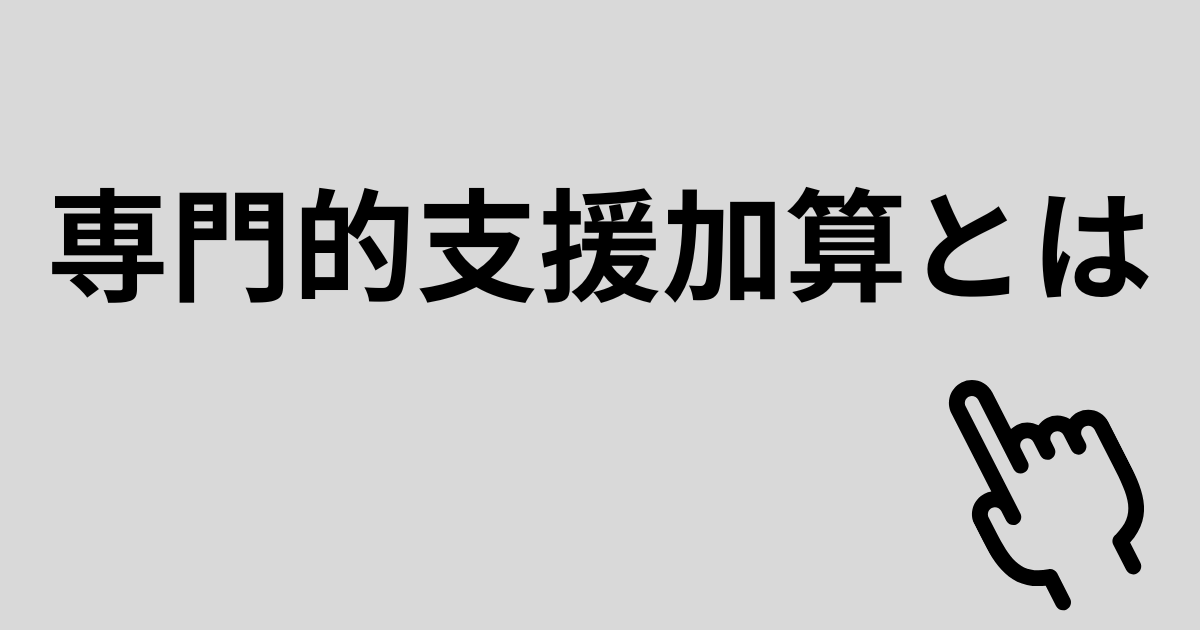本記事では、放課後等デイサービスに関わるすべての方に向けて、
2025年現在の最新情報をもとに「専門的支援加算」について、
制度の基本から支援内容の具体例まで丁寧に解説します。
制度の改定で混乱しがちなこのテーマですが、この記事を読めば、専門的支援加算について
事業所運営者、管理者、現場の支援員、そして保護者の方々にとっても役立つ内容です。
「専門的支援加算」とはなにか?
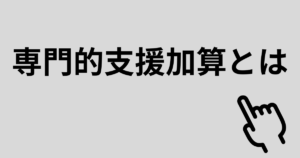
2024年度の報酬改定により、従来の「専門的支援加算」は2つの加算に再編されました。
・専門的支援体制加算(専門職の配置を評価) ・専門的支援実施加算(実際に支援を提供した場合に評価)
この加算は、発達支援が必要な児童一人ひとりに対して、より専門性の高い支援を提供できる体制づくりと、実践を促す制度です。
□専門的支援体制加算の詳細
対象になる「専門職」
以下の職種が対象となり、それぞれが専門的視点から支援を提供します。
・作業療法士(OT)
・理学療法士(PT)
・言語聴覚士(ST)
・公認心理師/臨床心理士
・公認心理師/臨床心理士
・社会福祉士
・保育士(児童福祉業務5年以上)
・児童指導員(同上)
専門職の支援例
・作業療法士(OT)感覚統合や運動支援など
・理学療法士(PT)歩行や姿勢の調整など
・言語聴覚士(ST)発音、コミュニケーション支援
・公認心理師/臨床心理士 情緒や行動面の支援
・社会福祉士 家庭・関係機関との調整
・保育士 食事や排泄、着替えなどの毎日のくらしを整えるサポート
季節行事や遊びによる気持ちの育ちを支える支援
家庭と連携した個別支援の取りまとめ
・児童指導員 宿題の補助や学習支援
ソーシャルスキルを高める集団活動1対1での落ち着いた関わりによる
気持ちや行動を整える支援
「常勤換算1.0」の意味と要件
専門職を「週32時間以上」勤務させることで、1.0人分としてカウントされます。
複数人のパート勤務者の合計でも構いません。
〇 算定できる単位数(日額)
定員10名以下:123単位/日
定員11〜20名:82単位/日
定員21名以上:49単位/日
※重症心身障害児の事業所はさらに高単位で設定されます。
専門的支援実施加算の活用法
〇 実施回数の具体例
月:4回通所→ 最大2回まで算定可能
月:8回通所→ 最大4回まで算定可能
月:15回通所→ 最大6回まで算定可能
回数制限は児童ごとに設定されており、支援提供があっても
上限回数を超えた分は算定できません。
加算対象となる支援内容とは?
・専門職が個別支援計画に基づいて実施する30分以上の支援
・児童の発達課題に応じた訓練やアプローチ(感覚統合、言語支援、心理支援など)
・支援内容の記録作成と、保護者への説明・同意取得
算定のポイント
1回150単位(対象児童ごとに)
月あたりの回数制限あり(例:月12日以上の利用→最大6回)
記録作成と運用の工夫
支援記録は簡潔かつ具体的に「誰が、何を、どう支援したか」明記
支援目的と成果の記録(例:「SSTを通じて友達とのやり取りが改善」)
記録フォーマットを統一すると職員間の情報共有が円滑に
加算取得の流れ
・体制整備(専門職の雇用・常勤換算の確認)
例:週20時間勤務のOTと週12時間勤務のSTを採用し、常勤換算1.0を満たす体制を準備。
職種別の役割を明確にし、シフト管理表を整備
・加算届出(自治体に必要書類を提出)
加算届出書、職員の資格証、勤務表、体制図などを準備し、
市区町村または都道府県の障害福祉課へ提出
届出期限に注意(概ね毎月10日など地域により異なる)
・支援計画の作成 実施例:利用児童Aに対して、
「発語が不明瞭なため、STが毎週1回発音訓練を30分実施」と計画に明記
支援内容は「専門的支援実施計画書」に記載
記録作成 ・保護者同意 支援前後に「個別支援記録」を記入
保護者に支援内容と目的を説明し、文書同意を取得
・加算請求(レセプト処理)
サービス提供実績を記録後、介護給付費明細書に加算を記載
月初に国保連へ電子請求。
現場での活用例 実践イメージ
・言語聴覚士(ST)による支援例 利用児童に対し、週1回30分の個別発音訓練
絵カードを用いた語彙強化、口の動かし方の模倣練習
毎月、保護者へフィードバックと家庭課題の提案
・作業療法士(OT)による支援例 利用児童に対して週2回の粗大運動・微細運動支援
トランポリンや平均台で体幹トレーニング、ハサミや紐通しで手指の巧緻性向上
・保育士 利用児童に対し、排泄・着替えの自立支援を毎回提供
季節の制作活動で感情表現を促し、集団生活への参加支援を実施
・心理士 利用児童に対して月4回のSST(ソーシャルスキルトレーニング)を個別に実施
「友だちと遊ぶ時のルール理解」や「怒ったときの気持ちの整理」の支援を実施
・看護師 医療的ケアが必要な児童に対して、吸引やバイタルチェックを毎回実施
護者との情報共有を密に行い、通所時の安心感を支援
・言語聴覚士 週1回、言語理解と発音訓練を30分実施
・作業療法士 週2回、粗大運動・微細運動の感覚統合アプローチを実施
・保育士 日常動作の習得や生活リズムの調整支援を継続的に行う
よくある質問(Q&A)
Q. パート職員でも専門職に該当しますか?
勤務時間を合算して常勤換算1.0を満たせば算定可能です。
Q. 保育士や児童指導員でも加算対象になりますか?
一定条件を満たした場合、専門職として算定可能です。
Q. 専門的支援加算は毎日算定できますか?
体制加算は毎日可能、実施加算は児童ごとの実施回数制限があります。
導入による事業所のメリット
専門的支援加算を導入することで、事業所には以下のような効果が期待できます。
・加算による安定した収益向上
専門職による支援を評価され、日々の利用ごとに単位が加算されるため、
財務面の安定につながります。
・保護者からの信頼性向上
専門職の支援があることで、「専門的な療育が受けられる施設」として
保護者からの信頼度が上がります。
・職員の専門性が活かされる環境づくり
専門職が役割を明確に発揮できる場が整うことで、チーム支援の質も向上します。
・自治体・学校との連携強化
専門職による記録や報告があることで、地域の関係機関との情報共有、
連携がスムーズになります。
他の加算との併用ポイント
専門的支援加算は、他の加算と併用して算定することができます。
以下は代表的な併用例
個別サポート加算(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ):重度障がいや不登校児支援との併算定
・医療連携加算 医療的ケアが必要な児童への支援を看護師が担当する場合に併用可
・保育・教育等移行支援加算 次の進路に向けた支援を行っている場合に加算対象
※併用には要件がありますので、自治体の指定ルールに沿って確認が必要です。
まとめ 制度理解から実践活用へ
専門的支援加算は、事業所が質の高い支援を提供するための大きな後押しとなります。
専門職の役割を活かした体制整備と記録運用によって、より多くの児童が適切な支援を受けられる環境を整えましょう。
現場での実践と制度の活用をつなげることが、子どもたちの笑顔と成長につながります。
児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準
について≪論点等≫
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001157665.pdf