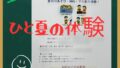~ひとりひとりに寄り添う、やさしい支援の仕組み~
放課後等デイサービス(以下、放デイ)は、障害のある子どもたちが、学校が終わったあとの時間や長期休暇中に、安心して楽しく過ごすことができる場所です。
子どもたちの発達や個性に合わせた支援を行い、成長を見守る場として、全国に多くの事業所が存在しています。
その中で、特に支援が必要な子どもたちに向けて、もう少し手厚く関わるための
仕組みがあります。それが「加配(かはい)」です。
このブログでは、「加配ってなに?」「どんなときに必要なの?」「加配加算って?」
といった疑問に、やさしく、わかりやすくお伝えしていきます。
保護者の方、現場で働く職員の方、放デイに興味がある方にも読んでいただきたい内容です。
【 加配とは?】

「加配」という言葉は少し聞き慣れないかもしれませんが、簡単に言うと、「子ども一人に対して、大人をもう一人つけること」です。
放デイでは、国が定めた最低限の職員数が決められています。
しかし、子どもの中には、集団の中で過ごすことが難しかったり、行動に不安があったり、医療的なケアが必要だったりする場合もあります。
たとえば、
・お友だちに突然手が出てしまう
・自分の気持ちを言葉にできずパニックになってしまう
・一人でトイレに行くことが難しい
・医療的な処置(たん吸引や注入など)が日常的に必要
こういった場合に、より安全に、安心して過ごせるように「もう一人、大人がそばにいる」ことが求められます。
この“もう一人”が「加配職員」と呼ばれます。
なぜ加配が必要なの?
子どもたちは、一人ひとり個性も違えば、安心できる条件も異なります。
みんなと一緒に活動したいけれど、不安が強くてなかなか踏み出せない子もいますし、他の子との関わりが難しくトラブルになりやすい子もいます。
大人がもう一人そばにいることで、不安な気持ちにすぐ気づいて声をかける。
危険な場面にすぐ対応できる。
子どもの「できた!」をすぐに受け止めてあげられる。
そんな支援が可能になります。
加配は、子どもが「安心して過ごすことができる環境づくり」
において、欠かせない存在なのです。
加配加算とは?
加配をすると、その分職員が増えるため、事業所にとっては人件費などの
負担が大きくなります。
そこで国や自治体は、「加配職員をつけた事業所に対して、報酬(加算)を支給しますよ」
という仕組みを用意しています。
これが「加配加算」です。
加配加算にはいくつかの種類があり、
職員1人分を加配した場合(加配加算Ⅰ):195単位/日
さらに手厚く職員2人以上を配置した場合(加配加算Ⅱ):390単位/日
医療的ケアを伴う支援がある場合(医療的ケア加算):約300〜450単位/日 ( 支援内容により異なる)
※地域や報酬改定により単位数が変更されることがあります。
ただし、加配加算は「ただ職員を増やしただけ」では受けられません。きちんと支援計画を立て、その子にどうして加配が必要かを説明し、自治体に申請して認められる必要があります。
※人員基準とは別です
ここで大切なのが、「加配職員は人員基準とは別に配置される必要がある」という点です。
放デイには、国が定める人員配置基準(たとえば、定員10名なら職員2名以上)がありますが、加配加算を受けるためには、その基準を満たしたうえで、さらに追加で職員を配置しなければなりません。
つまり、もともと必要な職員数を確保したうえで、「加配」としてもう一人つける、
という考え方です。
どんな子どもが加配の対象になるの?
加配が必要になるお子さんには、日常の集団生活の中で、
特に手厚い支援が求められる理由があります。
□加配が必要となる主なケース
・ 強度行動障害のある子
急に走り出してしまう、自分や他人を傷つけてしまう、
物を壊してしまうなど、突発的で強い行動が見られる場合、常時そばで見守り、
事前に予測・対応が必要です。
・ 医療的ケアが必要な子
たん吸引、胃ろうでの注入、発作への対応など、
専門的な配慮が必要な場合には、看護職や医療知識のあるスタッフが
加配されることがあります。
・ 感覚過敏やパニックを起こしやすい子
音や光においなどに敏感で、突然不安定になることがあります。
落ち着く環境づくりや、その子に合った関わり方をするために加配職員が必要です。
・ 社会的コミュニケーションに困難がある子
言葉でのやりとりが難しく、気持ちをうまく伝えられずにトラブルになることも。
そばにいる職員が、非言語のサインを汲み取る必要があります。
・ 移動やトイレなどに介助が必要な子
身体面での支援が必要な場合、職員が1対1で付き添う体制が必要になることがあります。
児童10人← 職員2人(人員基準)
【加配のある支援体制】
児童10人←職員2人(人員基準)+加配職員1人
(特別な支援が必要な子のため)
このように、「通常の職員数」とは別に、特別な配慮が必要な子どもに対して1名
(またはそれ以上)の支援者をつけるのが加配の考え方です。
加配職員に求められること
加配職員には、特別な資格が必須というわけではありませんが、以下のような姿勢やスキルが求められます。
・子どもの特性を理解する
・子どもの小さな変化に気づく観察力
・急な行動やトラブルにも落ち着いて対応する冷静さ
・チームの一員として周囲と連携する力
・一対一で関わることも多いため、その子にとって「信頼できる大人」になることが大切です。
現場での加配の工夫
実際の放デイの現場では、加配職員がつくことで、
子どもが次のような変化を見せることがあります。
表情が明るくなり、自分のペースで活動できるようになる
他の子との関わりがスムーズになる
不安やこだわりが落ち着いてくる
安心して通所できるようになる
たとえば、ある事業所では、毎回パニックを起こしていた子が、同じ支援者が付き添うことで安心感を得て、少しずつ活動に参加できるようになった事例もあります。
また、加配によって「安全な避難誘導」「落ち着いて食事をとる環境」「活動の選択肢を増やす」といった支援の幅も広がります。
児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について
最後に 加配は“その子らしさ”を支える仕組み
加配や加配加算という言葉だけを見ると、制度的で難しく感じるかもしれません。
でも、その根っこにあるのは、「その子がその子らしく過ごせるように、もう一歩近づいて関わる」ことです。
すべての子どもが安心して、笑顔で過ごせるように。
そのために、必要なときは大人の手をもう一つ、そっと差し伸べる。
加配は、そんなやさしい気持ちが形になった仕組みです。
放デイに関わるすべての人たちが、この制度を正しく理解し、必要な支援を届けられるように、これからも一人ひとりの声に耳を傾けていきたいと思います。